「雨が降るたびに頭が重くなる…」
梅雨の湿気や気圧の変化で、偏頭痛やむくみ、倦怠感を感じることはありませんか?「薬に頼らず楽になりたい…」そんな方へ、熊本の鍼灸サロンHarimoの鍼灸師が、東洋医学の視点からセルフケア方法をご紹介します。自律神経を整えて、今年の梅雨を快適に過ごしましょう!。この記事では、梅雨に起こりやすい体調不良、東洋医学的に梅雨とは何なのかを書いていきます!
【1.梅雨に起こりやすい体調不良】
梅雨とは、春から夏にかけて日本に停滞する前線のこと。だいたい6月から7月にかけて、梅が熟す頃という意味で『梅雨』というそうです。私は湿気が多くなると全身だるくなりがち。天気もどんより、気分もどんよりですよね。気圧の変化で頭痛が起きてしまうことも。他にも、むくみ、食欲減退、消化不良、めまい、ニキビなどの症状が起こりやすいと言われています。低気圧になると、体にかかる圧力も低くなるため、血圧の低下、血管拡張、冷えが起こります。これは自律神経の中の副交感神経が優位になりすぎて、体がリラックスしすぎることで起こります。
え!!!!交感神経が優位になる時に体調不良が起きるんじゃないの?
と、思った方もいるかもしれません。自律神経は交感神経と副交感神経のバランスが大切。どちらも同じくらい働いていなければいけません。片方が悪者というわけじゃないんです!
【2.東洋医学的に梅雨とは何なの??】
東洋医学では梅雨時期のことを『長夏』といいます。そして、いわゆる湿気のことを湿邪といいます。春=肝でしたが、長夏=脾です。この脾について解説しますね!
【脾の働きについて】
- 食べ物をエネルギーに変え、全身を巡らせる:食べ物を消化して、栄養やエネルギーにして全身に送る。脾が弱ると、消化不良、食欲不振、胃もたれ、倦怠感、食後の眠気、むくみが出る
- 血をコントロールする:血を体の中にととどめる働きがある。 脾が弱まると、皮下出血、月経過多、覚えのないあざ、顔色が悪くなるなどの症状が出やすくなる
主な作用はこの2つです!そしてこの脾が最も苦手としているものが【湿邪】!なのでこの梅雨時期は脾にとってはとても弱りやすい時期なのです。毎年訪れる梅雨の体調不良にできるケア、養生が何があるのでしょうか?
【3.鍼灸サロンHarimoのHaruが教える梅雨養生】
東洋医学の長夏と脾の関係について解説しました!次は、今から出来る梅雨養生について説明します。
✅甘味で脾の働きをサポート
脾は甘味との相性がとても良いです!ですがこの時の甘みは、砂糖を使ったお菓子の甘みではなく、自然な甘味のこと。食べ過ぎには逆効果になるので注意。
【改善方法】お米、さつまいも、かぼちゃ、とうもろこしを摂る
✅温かい飲み物で体を温める
温かいもので血行を良くしましょう
【改善方法】白湯、生姜湯、温かいお茶
✅軽い運動を行う
副交感神経が優位になりすぎると、体のスイッチがオフになりがち。少し身体を動かして交感神経をオンにしましょう
【改善方法】ストレッチ、早歩き、ジョギング、動きの多いヨガ
⚠️脾を弱らせるNG行為
- 甘いものを大量に摂る
- 小麦製品を大量に摂る
- 消化の悪いものを取る
これらは脾をさらに弱らせる原因に!
【まとめ】
今回は、梅雨時期の体調不良、東洋医学的な解説、そして梅雨時期の養生について話していきました!実践できそうなものはありましたか?♡
さいごにとっておきの方法を1つご紹介!
それは、鍼灸サロンHarimoの鍼灸治療を受けること!
✅鍼灸治療で使用するお灸、これは湿邪による症状に対してかなり効果的なんです!
お灸の火で水分をふき飛ばす効果があります!体の気の状態も整えてくれるので、梅雨時期の養生にはぴったり♡その他、偏頭痛や消化不良、食後の眠気、気分の落ち込みに対しても対応可能です!
気になる方は東洋医学治療が得意な熊本の鍼灸サロンHarimoの『心と体が解ける鍼灸治療』を受けてみませんか?
気になる方は下の画像をクリック!!
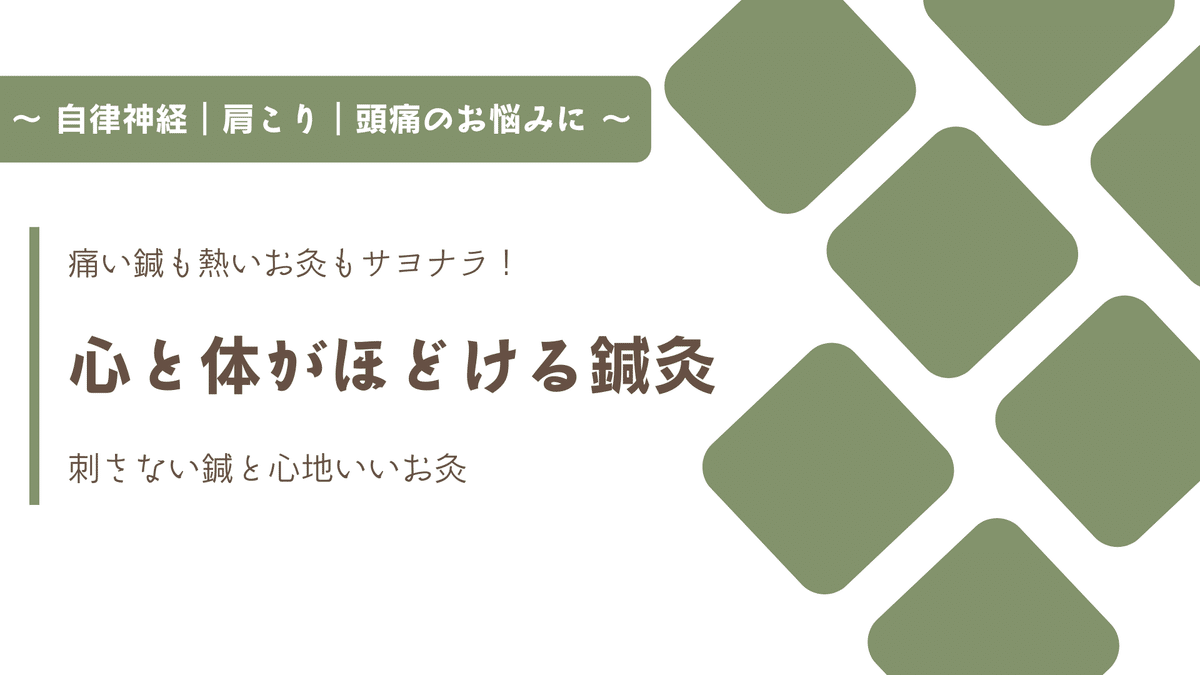
今日もお読みいただきありがとうございました〜♡
じめじめに負けない梅雨時期を送りましょ〜♡
質問やお問合せ・予約は公式ラインにて! 自律神経ケア|ストレスケア|PMSや生理痛ケアが得意な和室サロン♪ ◻︎どこよりも優しい鍼灸治療 ◻︎国産&オーガニックのハーブセラよもぎ蒸し
熊本県合志市須屋にある鍼灸サロン Harimo!(ハリモ)
◻︎リラクゼーションお灸ヨガ



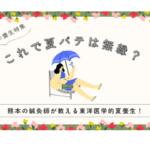

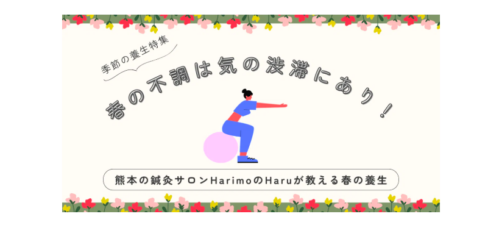
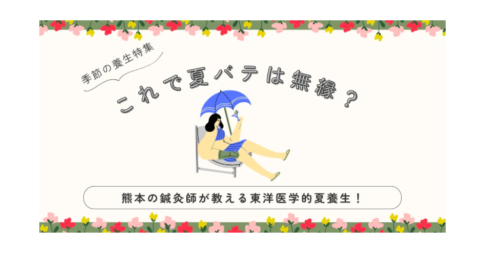
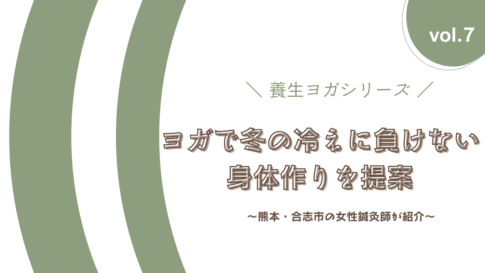
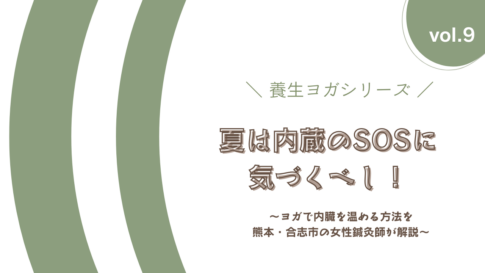

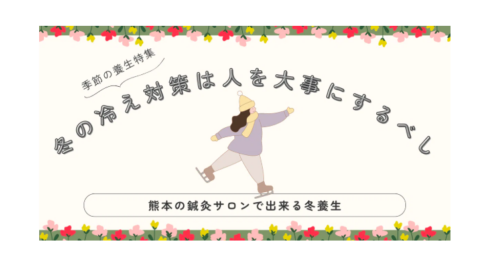
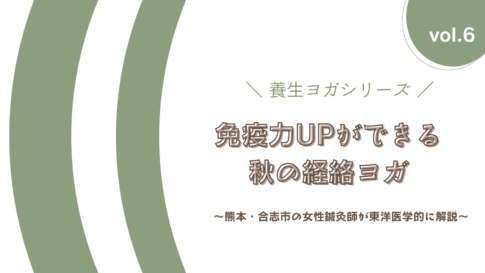



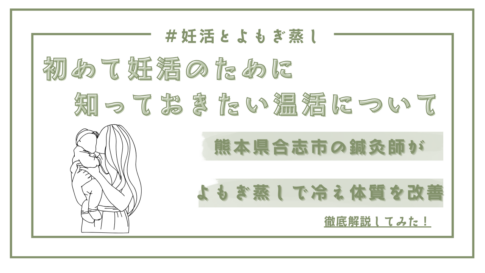
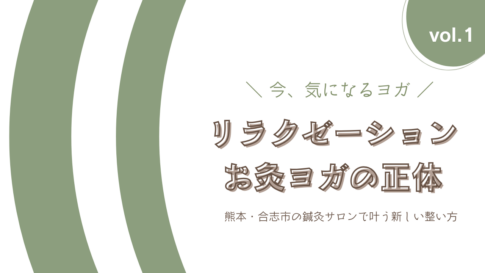
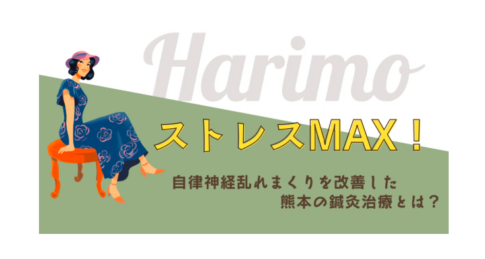
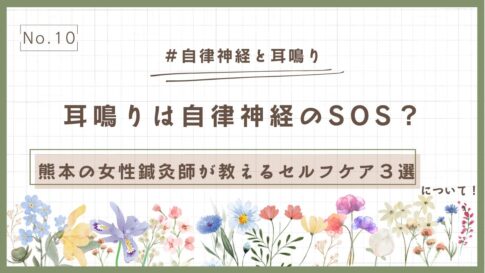
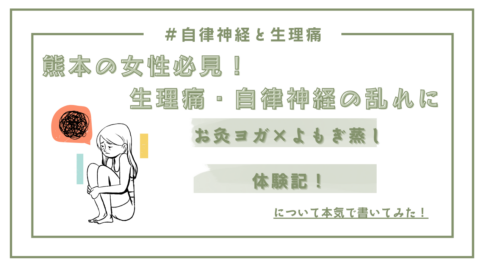
熊本・合志市でストレスケア/自律神経ケアが得意な『鍼灸サロン Harimo』を
開業している女性鍼灸師のHaruがこの記事を書きました♡